

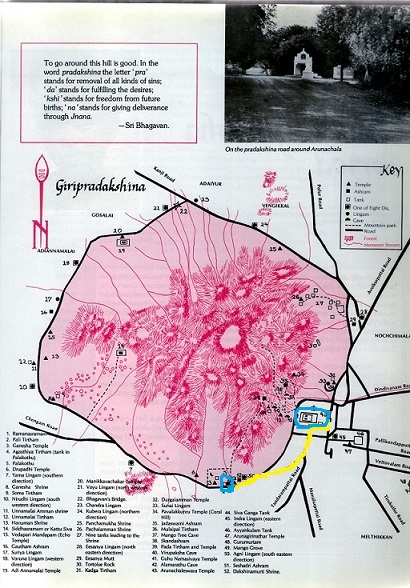
 |
そのまま東門から入場する。携帯やスマホなどの持ち込みは可、ただし「カメラ」は持ち込み禁止 |
 |
満月や大祭などの時は「入場制限」が行われ行列が並ぶのでかなり時間を要することがあるので注意。 パート7で説明したが、係員に寄る荷物チェック(それで「履きものを持ち込む」のもアウトになる)が実施されている。 (荷物だけでなく「服装チェック」をされ、不適切と判断されると入場を拒否される場合もある。) |
 |
右手に「千本柱のホール」 この中の一角に、ラマナがアルナーチャラに到着した際にしばらく籠っていた「パタラ・リンガム」がある(入場可能)。 お寺の中を撮影した16年は「大改修工事」実施中のため、あちこちに足場が仮設されたりシートがかぶせられたりしていた。 |
 |
インドならではの「お寺の象さん」・・・参詣者に祝福を与えてくれる。 ただし営業時間は昼間~夕方までなので、早朝及び夜間のギリプラダクシナの途上に寄っても象さんはいない。 |
 |
象さんの前に立ち(遮るものがなく至近距離で直に対面する・・かなりのインパクト!)、象さんが延ばしてくる鼻へ果物やコイン(鼻の穴の中に入れる)を捧げると・・・ |
 |
鼻で頭を撫でて祝福してくれるのだ!! 差し上げたお供物は隣に控えている「像使いに渡される(果物は象さんがそのまま食べる)。 日本の動物園では体験出来ないスペシャルなイベントであろう。 |
 |
三つ目のタワーの奥がご本尊が祭られている内陣となる。 |
 |
大寺院の一番奥の内陣。 治安状況によっては、非ヒンドゥの外国人はここへの入場が禁止となり、上記の門前で制止される場合もある。 (この写真はサイト管理人の撮影ではなく、ネットから拾ったもの) |
 |
この神殿の奥にご本尊(アルナチャレシュワラ神)が祭られている。 拝顔料20ルピー・神殿内は撮影禁止、非ヒンドゥの外国人でも参拝可能。 |
 |
神殿正面の上にずらりと並んでいるヒンドゥの神々の彫像群。 (モスクワの赤の広場とか北京の天安門人民広場のバルコニーでの式典で「政府のお偉方が横一列にずらりと並ぶ」あの光景のような感じ・・?)、 |
 |
これまでこの寺院の構造物はほとんど「白基調」で着色されていたが、16年の「大改修工事」で多くの彫像が極彩色に着色されるようになった。 |
 |
履き物を預けた場合は再び東門へ引き返すことになる。 (裸足でギリプラダクシナをしていたら、そのまま南門へ向かう方が近道となる。) |
 |
間近で仰ぎ見るとかなりの迫力である。 |
 |
東門の外側正面の様子。 |
|
|
東門は大寺院の正門であり、正面参道にこのようなアーケードが建てられている・・・ただし作られたのは近年。 |
|
|
東門側から見た様子。 |
|
|
アーケード天井に描かれた各種曼荼羅模様。 |
|
|
大寺院境内で休憩したらいよいよゴールに向かって出発、東門を出て右へ回り込む。 |
|
|
大寺院の外壁に沿って進む。 |
|
|
大寺院の南東の角。そのまま道なりに直進すると 「インドラ・リンガム(8方位東)」があるが今回は紹介は割愛。 この角を右折して更に壁沿いに進む・・寺院内で休憩しなかった場合はこれらのシャッターの閉まった商店の軒先を借りて休みと良いだろう。。 |
 |
反対側から見たコーナーの様子。 この写真のみ19年撮影、お天気が違っている(笑)。 |
|
|
見えているタワーは南門である。 |
|
|
シャッターを下ろした商店の店先は夜間にはサドゥさん達の簡易宿泊スペースになる。 大寺院内で休憩しない場合(深夜だと閉門している)ここまで来て、空いているスペースに腰を下ろして脚を投げ出して休憩することもできるが、 あるサドゥさんに「そこは俺の寝場所だからどいてくれ」と言われた経験あり(笑) |
|
|
通常はこんな具合に営業中。 |
|
|
屋根にずらりと並んだ聖牛ナンディ像。 |
|
|
南門タワー。東門よりは若干規模が小さいのだが、至近距離で見るとやはりでかい。 |
 |
寺院境内側から見た南門、ご本尊が祭られている神殿を出て右折すると近い。 |
|
|
南門。こちらからも入出場可能。 2004年撮影なのでフリー状態だが、現在では東門同様のセキュリティ・チェックがある(北門・西門も同じ)。
ギリプラダクシナを最初から裸足で歩いて来れば、境内で休憩した後にそのままこの南門から退場できるわけでもある(履き物を取りに東門に戻る必要がない)。 |
|
|
南門の正面から伸びている参道を直進する。 |
|
|
やがて商店街と寺院のタワーが見えてくる、商店や人家も多く夜間でも安心できる感じ、ただし狭い道ながら交通量は結構あるので要注意。
|
|
|
小さい寺院ながら立派なタワー。 |
|
|
更に直進するとやがて前方にモニュメントが見えてくる。 |
|
|
このモニュメントを中心としたロータリが第7分岐点。 ここを右折するのだが、例によって横断するのがなかなか厄介。 |
 |
先ずはモニュメントの近くまで渡ろう。 |
|
|
ロータリーの反対側。 |
 |
後方から右折・左折して進入してくる車両に注意!! |
 |
ギリプラダクシナとして歩く際には左側を歩く・・・セオリーに則り、行きかう車両の流れを十分見切って中央分離帯左側の道へ渡る。 |
 |
右折したらあとはひたすら直進、歩道も近年新設された(まだ整備途上だろう)。
|
 |
中央分離帯も近年新設されたものである。 |
 |
2014年撮影、こんな風に路肩の状況が良くないことが多いくて、裸足で歩くのには難儀なため、サイト管理人自身は当時は別ルートを歩いていた。 その後道路状況が随分と改善されたので、現在では毎回こちらのルートを歩くことになった。 |
 |
途上からのアルナーチャラの様子。 |
|
|
左手にある病院。 |
 |
主峰の形状がアシュラムで見慣れている形になってきた。 |
 |
左手にあるガソリンスタンド、ここを越えた辺りにサイト管理人が馴染みにしている床屋さんがある・・・ので、個人的にはここまで来ると日常生活圏内へ戻ってきた感じになる。 |
 |
「馴染みの床屋さん」前辺りからの風景。 |
 |
左手にある学校 |
|
|
やがて前方に「アシュラム門前の道」との合流点が見えてくる。 |
|
|
間もなく合流点。 |
|
|
合流点、ここを左折する。 |
|
|
アシュラム正門まで残り10分弱というところ。 気分的にはこの合流点まで来たら、マラソンでいえば・・ 「いよいよ先頭集団は競技場に戻ってまいりました、後はトラックでの最後の勝負です!!」 とでもいうような感じ?である(笑) |
|
|
もうこの辺りは、普段のアシュラムでの日常生活での 「徒歩行動圏内」である。 |
|
|
左側にあるガネーシャのお社。 天井が高くてスペースがあるので、お祭りのときなどは 巨大なご神像が登場して華やかな雰囲気に包まれる。 |
|
|
その対面にある沐浴場。 この写真では主峰山頂に雲がかかっているが、ここからの眺めもなかなか素敵である。 |
 |
19年撮影、ゲートの部分に新しい建物を建築中。 |
|
|
同じ沐浴場の2004年の撮影。 インド名物「牛糞燃料」を乾燥させている。 最近では田舎の方に行かないとなかなか見かけ難いかもしれない。 |
|
|
やがて右手に「アグニ・リンガム(8方位の南東)」へ続く入口が見えてくる。 |
|
|
入口。この先を入って右側に「アグニ・リンガム」がある。 この通りは外国人向けに商売している店が多く、宿やレストランも結構揃っている上に、評判が良い「シャンティ・カフェ」というエージェント(「日本円両替可能」)も営業している。 更にはアシュラムの「裏門」にも通じているので、日常的によく使う道である。 |
|
|
こちらが「アグニ・リンガム(8方位の南東)」。 8方位リンガムの中では拍子抜けするほど簡素。 |
|
|
通りに戻って左側にある祠。 後ろ側にも外国人向けショップが並ぶ。 |
|
|
この界隈では規模の大きなレストラン「オウロユウシャ」。 アシュラムの晩御飯に間に合わない時間帯で歩いた際には、戻ってきた際にここで食事ができるだろう。 |
|
|
その対面にある「シュリ・セシャドリスワミ・アシュラム」。 セシャドリ・スワミはラマナより先にこの地に来ていた聖者さんで、 ラマナがやってきた最初期の頃に彼の面倒を見ていた。
当然ながら地元にはこの聖者さんの信奉者も多い。 またこのアシュラムのゲストハウスには外国人も滞在可能なので、ラマナアシュラムの滞在許可期限が過ぎた後もアルナーチャラに滞在したい場合の居住先の候補の一つである。 |
|
|
左手に見えてくる「ドゥルガー寺院」。 「アルナーチャラのビューポイントその2」でも紹介している。 |
|
|
この辺の右側は既にラマナアシュラムの敷地である。 |
 |
19年撮影、道路右側もタイルが敷設された。 |
 |
左手にあるステートバンクのATM、アシュラムから一番近いATMである。 |
|
|
ラマナアシュラムの車両専用通行ゲート。 工事や物資運搬用大型車両の出入の為のものだが、 正門前が工事中だったりする際には、人間もこちらから出入りするケースがある。 |
|
|
ダクシュナムリティのシュライン。 プージャの際にはかなり信奉者が参集する。 |
|
|
さあ、アシュラム正門が見えてきた!! この道を向こうへと歩いて行ったのにこちらから帰って来るのがなんだか不思議な感じでもある。 (1周したのだから当然なのだが・・笑) |
|
|
アシュラム正門へ帰着。 これにてアルナーチャラ巡礼路1周終了、 ギリプラダクシナは以上で完結!!
|