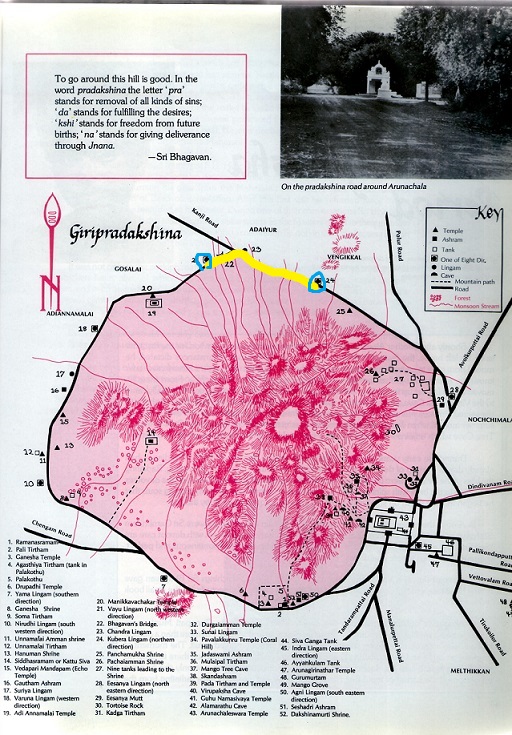
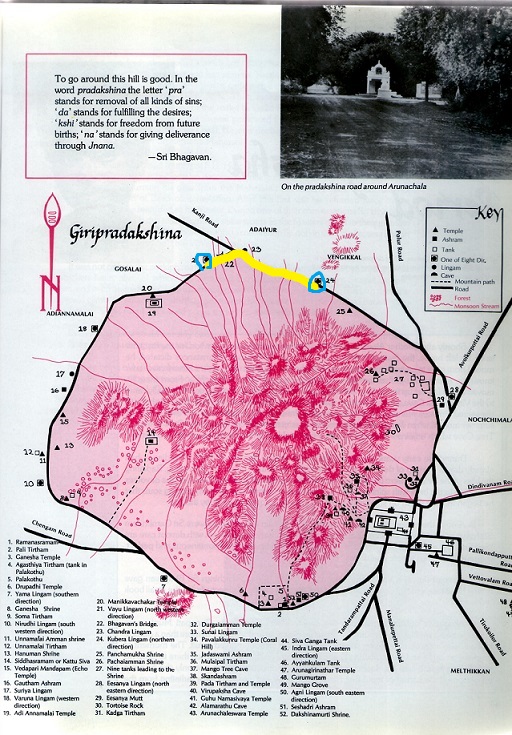
 |
ヴァーユ・リンガムの対面にある寺院。 |
 |
19年撮影。 この建物は何だろう?・・宗教施設ではあるだろうが。多分これから内側が増設されていく・・・と思われる。 |
 |
「ギリプラダクシナ・パス」も終わりに近づいていく。 |
 |
19年撮影、上記のやや手前側。 歩道上にアーケードが増設されている。 |
|
|
近年はこういうカラフルなデザインの建物が増えた。 |
|
|
こちらも然り、建物は出来てもテナントはまだ空家というところも多い。 |
|
|
「お友達犬」の一匹・・・自分の縄張りの範囲まで一緒に歩いてくれる(ビスケット目当てだが・・笑) |
|
|
14年撮影、こちらも最近できた施設。 |
 |
19年撮影、道路右側に出来た寺院 |
 |
上記の隣にあるこの建物のところまで来たら・・・ |
|
|
対面にあるこの構造物こそが実は「バガヴァン橋」である。 かってラマナが頻繁にギリプラダクシナをされていた時は、この橋の欄干に腰を下ろして休まれていた・・・とのこと。 ただし残念ながらこれは2代目である・・・。 |
|
|
2004年に新造された頃の2代目欄干。 誠に遺憾ながらサイト管理人の手元には「初代」の写真が無い。 (初代はもっと腰高で、サイト管理人が座っても足が地面にとどかかなかった覚えがある・・脚の長いラマナならきっと地面まで足がとどいたのであろう。) 施工当局としては「初代欄干」がラマナ信奉者にとっての聖遺物であることには関心がなかったわけで、しばらく放置されていたがいつのまにかどこかへ撤去・処分されてしまったらしい・・・。 |
|
|
反対側欄干・・・ご覧のようにこれは「橋」なのである。 雨季には小川になる。 |
|
|
欄干に座ってこれまで歩いてきた方向を見た様子。 位置的にはちょうどアシュラムと御山を挟んで180度反対側に位置するためアシュラム正門から出発した場合は、 先ほどの「ヴァーユ・リンガム」よりも、この橋がギリプラダクシナ全行程の中間地点・・という感覚である。 |
|
|
14年撮影、欄干に座って正面のアルナーチャラを臨む。 |
 |
19年撮影の同じ建物。 |
 |
14年の写真に比べると左側に建物が増設されている。 |
 |
04年撮影の全く同じ場所である・・・以前はアルナーチャラの全景を拝むことが出来た。 |
|
|
ラマナもここに座ってこの様子をご覧になっていたのであろう。 |
|
|
進行方向の様子。 先の方に分岐点が見えている。 ティルヴァンナマライ(町の中心)まで5キロの標識。 |
|
|
「ギリプラダクシナ・パス」はここで終了する。 |
 |
19年撮影の同じ場所、随分様子が変化したことが分かる。 |
 |
新設された休憩スペース。 |
 |
ベンチからアルナーチャラを臨む、全行程の半分の地点だけにここで休憩するのも良いだろう。 |
|
|
アシュラム正門から出発した場合はここが2番目の分岐点。 もちろん右折横断するわけだが車の通行に十分注意すること。 |
|
|
ここからは「クベラ・リンガム」を超えて第3分岐点に至るまで、ほとんど直線のコースである。 交通量は多いが案外歩きやすいゾーンである。 |
 |
この辺りの歩道は車道と同じぐらいの幅である。 |
 |
歩道に座り込むのもまた面白かろう(笑)。 |
|
|
2004年撮影。 |
 |
19年撮影のほぼ同じ場所、アルナーチャラの景観は変わらない。 |
|
|
古くからあるチャンドラ・リンガム |
|
|
この寺院は新しい。 |
|
|
商店は道左側に多く点在する。 右側には政府系の建物や住宅が多い。 |
|
|
この辺りはまだまだ空地も点在するが、先に進むと住宅造成地がぐんぐん拡大されてきている。 |
|
|
かなり大きな寺院だが古くからのものではない。 満月時などは門前でギリプラダクシナ巡礼者のために、 「プラサード」の炊き出しを実施している。 |
|
|
2004年撮影の同じ寺院。 ヤシの木がまだ背が低かったのが分かる。 |
|
|
これも最近できた祠・・・看板の人物が寄進したのであろうか? |
|
|
昼間に歩くとこの辺りの御山が複雑な形状をしていることがよくわかる。 (単独峰ではなく複数の副峰によって稜線が形成されている。) |
|
|
アシュラム敷地内でもよく見かけるが、寄生木が気根をずるずると降下中・・・この写真は2004年撮影なので現在は着地しているはずだ。 |
 |
19年撮影の同じ樹木、一部が着地している。 道路右側にも歩道が敷設されている。 |
 |
どうやら2段階に渡り歩道を敷設したようだ。 因みに写真には残していないが、17年の時は全域に渡り一斉工事中で、砕石等が散乱していて、裸足で歩くのがかなりきつかった覚えがある。 |
 |
数年前に出来たスポーツクラブ、なんと「スイミング・プール」がある!! |
 |
19年撮影スイミング・プール・・・予想に反して?かなりきれいな水であった。利用料金は100ルピー。 |
 |
利用者の話によると、インド人は「レジャーとしての水泳」という習慣が無いので、子供たちが遊びに来るほかは、たまに外国人が泳ぎに来る程度で、ほぼ「独占して泳げる」そうである。 ラマナ・アシュラムからは殆ど真反対に近い・・のが難点かも(笑)。 |
 |
ここにも新設された休憩スペースがある。 |
 |
19年撮影、いずれアーケードが増設されるのだろうか? 8方位北のクベラ・リンガムのすぐ手前である。 |
 |
道路反対側にあるクベラ・リンガムの標識。 |
 |
クベラ・リンガムの入口。 |
|
|
「クベラ・リンガム」の入口正面。 どこがこの天蓋を寄進したか一目瞭然、地方都市ながらも昨今は高級ホテルもあちこちに出来てきている。 |
|
|
8方位の北に位置する「クベラ・リンガム」。 クベラ神は海洋神らしく、この神様が日本に来て 「金毘羅さん」になっているそうだ。 |
|
|
2004年撮影の「クベラ・リンガム」 これまで見てきた8方位リンガムとは異なり、以前から立派な構造だったようだ。 それだけここの信奉者の寄進が昔から多かった・・ということになるのだろうか? そうだとしたら結構ご利益が期待できるのかもしれない(笑) |