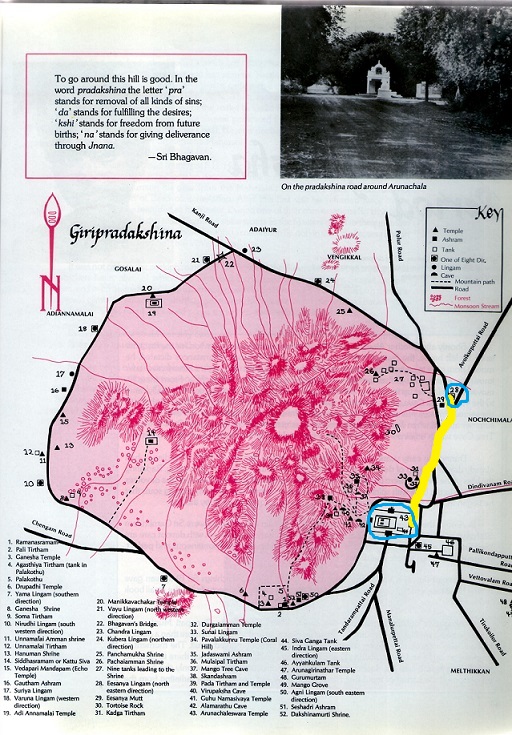
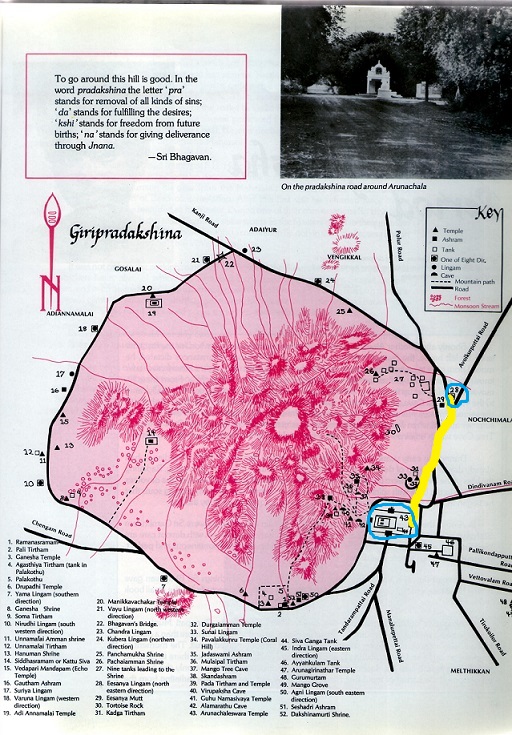
|
|
エーサニア・リンガム近くからのアルナーチャラ。 2004年撮影 |
|
|
上記の囲いの中・・沐浴場。2014年撮影 |
 |
19年撮影、新しくできた寺院。 |
 |
こちらも19年撮影、以前には無かった・・・のかな? |
|
|
エーサニア・リンガムからしばらく進むと、 第4分岐点が見えてくる。
|
 |
第4分岐点手前右側にある学校。 |
 |
父兄参観会かな? |
 |
2019年撮影の第4分岐点 |
 |
ここを右折して新道との合流点に向かう。 |
|
|
14年撮影の第4分岐点。 |
 |
第4分岐点を渡ったところで仰ぎ見るアルナーチャラ。 |
 |
新道との合流点へ進む。 |
|
|
第4分岐点14年撮影の同じ道。 |
 |
合流点手前左側にあるクリスチャン系の学校。 |
|
|
第3分岐点で別れた新道とここで合流する。 その先にはティルヴァンナマライの繁華街・・・。 信号機もあるが動いてないこともしばしばである。 |
|
|
合流点から見たアルナーチャラ。2004年撮影。 |
 |
合流点から見たアルナーチャラ。2019年撮影。 |
|
|
新道から進入してくる車両には十分注意すること。 この先の道路には中央分離帯があるので、新道から入ってきた車両の流れは、歩いている左側車線にどっと流れ込んでくる。 |
|
|
ティルヴァンナマライの繁華街。 ここを直進していく。 |
 |
2019年撮影、繁華街はあんまり変わっていない(笑)・・・昔からの大喧噪ゾーン。 |
|
|
しばらく行くと左側にこの町のバス・ステーションがあり、 こちら側はバス出口ゲート。 |
|
|
バスもまた「歩行者優先」という意識は全く持ち合わせていないので、要注意。 この出口ゲートも順序良くバスが出てくるのではなく、我先を争うように数台がまとまって出てくる・・こともしばしばである。 |
|
|
バス・ステーション。2004年撮影だが現在も様子はあまり変わらない。 この町へバスで来た場合の終着点・・アシュラムまで約3キロの位置。 ただしバンガロール方面から来る場合は、アシュラム正門前を通って来るので、車掌に頼めばアシュラム正門前で降ろしてもらえる。 |
|
|
対面にひしめくホテルやレストラン。 いわゆるインドの安宿・・・当然ながら大通りに面しているから静かな環境は望めないが、深夜到着した場合には便利。 南インドの安宿はほとんどが「24時間制」を採用しており、チェックアウトはチェックインから24時間後。
バス・ステーションを利用する大勢のお客さんが利用するので、こういうところのレストランは結構美味しかったりする。 |
|
|
ギリプラダクシナ全ルート中、もっとも交通量が多く騒めき犇めいているゾーンであろう。 車両だけでなく、バスから降りてきた人たちでも溢れている。 |
|
|
2004年撮影のもの・・・当時はまだ「中央分離帯」がなく、仮設のフェンスで道を分けていた。 |
|
|
バス・ターミナル外側にもずらりと商店街。 道の路肩にはバイクがずらりと並んでいるので、歩道を歩く方が歩きやすいだろう。 |
|
|
そしてバス入口側ゲート。左折して進入するバスに巻き込まれないように注意。 また反対車線からも右折進入するバスもあるわけで、しつこいようだが「歩行者優先」という意識は毛頭ないことをお忘れなく!! バスには入口だが、送迎の車やリキシャがこっちから出てくることもある・・のでそれにも注意すること。 |
|
|
バスターミナル入口ゲート側内部の様子。 |
|
|
バス・ターミナル周囲のオートリキシャだまり。 アシュラムへの行き来は荷物もあるだろうから、ギリプラダクシナでない限りは利用した方が便利である。 料金交渉をお忘れなく!・・19年現在アシュラムまで80ルピー見当が「外国人料金相場」(笑) |
|
|
この道でももちろんアルナーチャラは見えている・・・のだが、なかなか意識を向ける余裕がないかもしれない。 |
 |
やがて行先に見えてくるモニュメント。 ここがロータリー状の(第5)分岐点になっている。 |
|
|
ギリプラダクシナとしては「道なりに直進」なのだが、道の左側を歩いているので、このロータリーを最短距離で直進して突っ切るためには、一度車線を横切り中央分離帯側へ寄る必要がある。 |
|
|
画面右側に伸びている道の方に行くのだが・・・横断がかなり厄介、要注意ポイントである。
|
|
|
時にはびっしりとバリケード封鎖されていることもある。
|
|
|
その場合はこのようにロータリーに沿って右回旋・・・ だがぼんやりしているとご覧のようにこの隙間にバイクが突っ込んでくる。 |
|
|
もちろんバイクとて「歩行者優先」という意識は全く持ち合わせてないことは言うまでもない。
|
|
|
左方向からロータリーに進入してくる車両にも要注意。 因みにこのバスは「鉄道駅」の方から来ている。 |
 |
ロータリーの反対側(渡り切った側)から見た光景。 |
 |
なかなか印象的な寺院とご神木である。左側の道を向こうから歩いてくることになる・・・ので立ち寄ってみるのも良いだろう。 |
 |
なかなか見事な御神木であろう。 |
 |
ロータリーの中ほどから見えるアルナーチャラと寺院。 |
 |
ロータリーの反対側に出たら、次はこのバリケードを突っ切るのである。 |
|
|
右側に伸びている道が進行ルートなので・・・ |
|
|
こんな風に歩行者用に?バリケードに隙間があったりする。 ほとんどこの場所だが、ごくまれに隙間がないこともあるが、その場合は探せば必ずどこかにある(笑) |
|
|
ようやくこの道へ出ることが出来る。 この「魔のロータリー」を回避することは可能だが、大回りになって時間を要することになる。
|
|
|
第5分岐点(「魔のロータリー」)を渡り切って一安心・・ではあるが、この道は道幅が狭くなる上に対面通行なので、大型車両同士がすれ違う場合に近くを歩いているとかなり危険を感じる。 |
|
|
この通りからも建物の間からアルナーチャラが望める。 |
|
|
途中左側にある市の環境保護局。 我々がここに用が出来ることは滅多にないのだが、アルナーチャラ山頂へ登る際に諸般の事情でここが発行する「パーミット(許可証)」が必要になるケースが生じることもある。 |
|
|
さてアルナーチャラへ意識を向ける余裕があるだろうか? |
|
|
通りにあるお社にもご挨拶を忘れずに歩きたいところだが・・・ |
|
|
どの時間帯でギリプラダクシナをするにしても、右回りである以上正門から出発した場合は4分の3以上を歩いてきて、肉体的な疲労度はピークになっていることであろう。 |
|
|
くたびれた身体を引きずるように歩き続けていると、やがて前方に、アルナチャレシュワラ大寺院の巨大な東門タワーが姿を見せ始める・・・そこに向かってもうひと歩き頑張ろう。 |
|
|
しかしぼんやり油断していると、こんな具合にすぐ脇をバスが疾走してくる。 |
|
|
もちろん常にアルナーチャラはこちらをご覧になっている。 |
|
|
次第に近づいてくる東門タワー。 あそこに到達すれば一応この「最大の難所」は終了する。 |
 |
19年撮影、あまり変わらない。 |
|
|
反対車線の路肩に駐車している車をかわそうとして、こちらに大きく頭を振って来る場合も多い。 また大型車両同士がすれ違うときは自分から路肩に退避すること。 相手は「歩行者優先」という意識は全く持ってない・・ことを絶対忘れてはならない。 |
|
|
そしてここが第6分岐点。ここを直進して大寺院の参道に入るのだが、これまた横断するのが大変厄介なところ。 先ほどのロータリー同様に、サイト管理人はここを「魔の十字路」と称している(笑)。
|
|
|
大型重機が左折侵入してくる・・・見通しが悪いのでぎりぎりまで接近しないと左折車両の有無がわからない。 |
|
|
もちろんバスも入って来る。 運が悪いとこの時後方からも大型車両が来て「お見合い」状態になり、歩行者はいやでも隅っこに追いやられる。 追いやられる先に牛がいたり水たまりがあったりゴミが落ちてたり・・もしばしばで、 そういう時に裸足だと躊躇したくなるが、まごまごしてると今度はバイクや自転車にぶつけられる羽目になる。
|
|
|
取りあえずバリケードの中まで行きたいが・・・ |
|
|
バリケードの内側であっても、バイクは隙間さえあれば躊躇なく進行してくる。 |
|
|
さあ、何とかここを渡らなくてはならない・・・・ |
 |
躊躇しているとバスが疾走してくる・・・反対側(渡り切ったところ)からみた光景。 |
|
|
我彼の距離感がお分かりであろうか?
もっとも先ほどの「魔のロータリー」もここも、拍子抜けするほど簡単に横断できる場合もあり、 「今日の運試し?」的な感じがしないでもない(笑) |
|
|
なんとか渡り切って一安心、取りあえずこの道には大型車両は入ってこない。 |
|
|
とは言え、参道だけに人は多いしリキシャやバイクは傍若無人に走り抜ける・・のでやはり油断は禁物である。 |
|
|
脇にいらっしゃる神様にご挨拶を忘れずに行こう。 |
|
|
もうすぐ大寺院である、あと一息!! |
|
|
こちらにもご挨拶して辻に出ると・・・ |
|
|
アルナチャレシュワラ大寺院の一角へ(北東のコーナー)。 右に見えているのは北門タワー。 アシュラム裏門からの登山道を歩くと、 最後にはこの向こうの北西コーナーに出るので、そのまま大寺院を参拝するにはこちらに向かって歩いてくることになる。 |
|
|
ここら辺から仰ぐアルナーチャラの雄姿。 |
|
|
左折して東門タワーへ向かう。 |
|
|
東門タワーの入口前のフェンス。 これがあるのでこの先は車両進入禁止。 |
|
|
同時に人間の方もこの隙間から入ることになる。 |
|
|
東門入り口前の様子。 寺院に入場する場合は必ず裸足になること(ここに写っている人たちの足元に注意)。 履き物は持ち込み禁止なので、周囲にある「履き物預かり」に預けるか、門の脇に放置する。 (結構預けずに置かれている履きものがある・・もちろんこの場合盗難に遭う可能性あり) |
|
|
至近距離で仰ぎ見ると首が痛くなるほど巨大、 全高50メートルと言われている。
因みにこの東門が正門になるが、他の3つの門からでも入退場可能である。
|
|
|
境内は3重構造になっていて、向こう側に見えているタワーは西門ではなく内陣への入口(さらにその奥にも門があり境内が続く)。 インドのヒンドゥ大寺院としては大変珍しいことに、最奥に鎮座ましますご本尊を、外国人(非ヒンドゥ)でも参拝することが出来る。 ただし境内は一応撮影禁止。 カメラを向けると注意される・・・のだが、昨今は殆どのインド人もスマホや携帯を持ってるからそれで撮影している(笑)。 |
|
|
上の写真は2004年撮影、こちらは2014年撮影。 実は大きな違いがあるのだがお分かりだろうか?
この写真左下の一角にフェンスと金属探知ゲート、及びポリスボックスが設置されているのが写っている。 2004年には、そういうものはなく自由に入退場出来たのだが、現在は入場時はこのフェンスの内側から金属探知ゲートを潜り、 (荷物だけでなく「服装チェック」をされ、不適切と判断されると入場を拒否される場合もある。)
インドでも最大級のヒンドゥ寺院であるので、「ムスリム過激派」のテロ攻撃対象となる可能性を否定できない・・・からである。 |