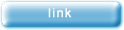アシュラム生活についての概要説明&注意事項 ・・ラマナアシュラムではどのような日常生活が営まれているか?
重要!! アシュラムからの訪問者への注意喚起→ 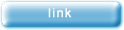
- アシュラム内は「禁酒・禁煙・菜食・静寂」を遵守すること。
- 楽器演奏は不可、音楽を聴くこと自体は禁止されてはいませんが音量に十分注意すること。他のゲストと話をするときも各ホール内と周辺では最大限の注意を払うこと。
- 各ホール内と周辺は靴を脱ぐこと(鞄に入れての持ち込みも禁止です)。
その他には
- 盗難に注意すること・・・泥棒はどこにもいます、外国人は狙われやすい。貴重品はオフィスに預けた方が無難です。
- 山歩きや夜の巡礼行は女性は出来るだけ単独行動を避けること。ごくたまに強盗事件があります。
- 動物には十分注意すること。殆どの犬は放し飼いですし、サルどもは引ったくりの常習犯です。頭上の孔雀たちはお構いなくウンチをします。気が立っている牛にどつかれるとか、沐浴に来た象(野生ではないがたまに道ですれ違うこともある)に興味本位で近づかないように!
- アシュラム内のいかなる場所も事前の許可を必要とせず自由に撮影できます。儀式の撮影・録音も自由です。(ただし瞑想ホール内では他の人の迷惑を考えるべし)
・・・・これは大変珍しいことです−理由としておそらくは、かってバガヴァン御自身が写真撮影について全く頓着していなかったことに由来するのではないか?と思われます。インドの聖者さんとしてはかなりの数の写真や動画が残されていますし、現在にあっても信奉者が家宝として秘蔵してきたものが初公開されたりするほどです。
ゲストルームについて
重要!! アシュラムからの注意喚起→ 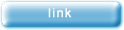
インドの安宿と同じレヴェルですがメンテナンスはかなりしっかりしていて清潔に保たれていると感じます。
- 基本的にベッド・机・椅子の3点セットのみのシンプルな部屋です。天井に扇風機が着いてます。
- ゲストルームは複数のエリアに分かれています。大まかに言ってアシュラム主要施設のある敷地内にある部屋は築年数が古いのですが、「アシュラム内」という感じが強く、とても静かです。
- 本体敷地以外にも年々「飛び地領」的にアシュラムが所有する土地は増えていて、新しいゲストルームはそのような敷地に建設されています。中には中級ホテル並みの立派なゲストルームもありますが、本体敷地まで少々遠かったり「マンション形式」の為、結構お隣さんがざわざわと煩かったりします(笑)」
- トイレは西洋式もありますが古い部屋はインド式ですので紙を使わないインドスタイルをお薦めします(慣れてしまえばあれほど快適なものはないのですが・・)。最近(2011年現在)は古い部屋のトイレも改装され殆ど西洋式になってしまいました・・(笑)
- シャワーはあっても使い難かったりして結局はバケツに水を貯めて浴びる方が楽だったりします。新しいゲストルームは太陽熱温水が使えるところもあります。 最近(2016年現在)は古い部屋も含めてほとんどのゲストルームに「ホットシャワー」が供給されるようになりました。
- ベッドシーツと枕カバーは支給されますが、上に掛ける物はないので持参すること。
- 洗濯はアシュラム外にある洗濯屋に頼めますが、自分の着る物くらい手洗いで済みます。
- ホテルの部屋ではないので掃除は自分ですること。
- 部屋の中での飲み食いは自由(ただし禁酒・禁煙・菜食です、日本から持ち込む食品も要注意)、甘いお菓子などは気をつけないとすぐに蟻にたかられます。小さな赤蟻は攻撃的ですぐ噛み付くので注意。
- ・・・・・こういう簡素な部屋で所持品は鞄ひとつという生活を体験するのは普段の生活を痛烈に反省する契機にもなります。
ゲストはダイニングホールでの食事が供されます。もちろん南インド風ピュアヴェジタリアン料理です。ここの食事は凄くおいしいと定評があります。写真による紹介はこちらへどうぞ(幾つかは文中から直接リンクしています)!
- 食事時間は朝食が07:00、昼食が11:30、(午後のお茶が16:00、)夕食が19:30となっていて、鐘の合図(実は鉄道レールの切れっ端を叩いている!・・・)で知らされます(お茶時間は合図無し)。あまり遅れると食べ損ないますので注意。昨今では訪問客増大の為に結構行列ができるようになりました。開始時間10分前位から場合によっては30分前から並び始めます。
- 普通はバガヴァンが居住されていた頃からある古いダイニングホール(つまりバガヴァンもそこで皆と一緒に食事をされていました)で食べますが、人が多いときは97年に増設された新しいダイニングホールになります。新しいホールが出来て以降は食事の順番待ちは殆どありませんが、ごくたまに1度に収容できず、2回目を待つ場合があります。昨今では訪問客が増大し新しいダイニングホールをメインに併用することが殆どになりました、収容しきれない場合古いホールも併用されます。
- ダイニングホールの床にずらりとバナナの葉っぱのお皿が並んでいますので、その前に座ります(テーブル席は体の不自由な人専用です)。どこに座ればいいかまごついたりしますが、様子を見ていればわかります。外国人は一箇所にまとめられます。男女同席です。
- 手で食べるのが基本ですが、苦手な人はスプーン、フォーク、箸などを持参して使って構わないです。葉っぱの皿を使わずに自前の食器に配膳してもらうことも出来ます(・・・・せっかくですから葉っぱのお皿で食べたほうが楽しいです、最近は街中のレストランでもこの葉っぱのお皿はあまり見かけなくなりつつありますしね)。
- 皆で同じものを食べますが、外国人には「ノン・スパイシー」なものを配膳しています。昨今では訪問客が多い場合は「ノン・スパイシー」調理は提供されないケースが増えました。インド人向け「スパイシー」の方を食べたい場合は配膳してくれる人に申し出てください。自分の好きな食べ物を持ち込んでも構いませんが、あくまで「菜食限定」であることを忘れずに!
- 食べ始めるための特別な儀式はありません、どのタイミングで食べ始めても構いません。インド人も外国人もそれぞれの「食前の祈り」を奉げる人もいれば、さっさと食べ始める人もいます。静かに黙々と食べる人もいるし、賑やかにお喋りしながらの人もいます。小さな子供達のいる家族はわさわさしながら食べますしね。
- 飲み水は「浄水器」を通したものなので心配は無用です。ホールの片隅に給水機があり、空き瓶を持参して給水し部屋に持ち帰ることも出来ますが、ホールが開いている時間(つまり食事とお茶の時間)でないと利用できないので注意。現在はこの給水器から配管を建物外に延長した蛇口があり、ホールに入らなくとも自由に給水できます。
- アシュラムの食事にしては結構バラエティに富んでいます。甘いお菓子やフルーツサラダが出たりもします。とりわけ「乳製品」はアシュラム内の牧場からのものなので大変おいしいですよ!
- 「飲み物」は朝食ではミルクコーヒー(時としてチャイ)もしくはミルク・・・両方もらうことも出来ます、昼食はバターミルク(飲むだけでなくご飯にかけて食べる)のみ、お茶の時間はチャイかミルク、夕食はミルクかバターミルク・・・・この2つは同時に摂ると後でおなかが苦しくなるので注意!コーヒーやチャイはノンシュガーのものも用意されています。
- おかわり自由ですし、何も言わないとどっさり継ぎ足されてしまいます。食べ残すというのは失礼ではないにしても注意されることもありますので、配膳してくれる人に明確に意思表示しましょう、英語で通じますがタミル語で「クンチュ(少し)」と連呼すればいいでしょう。もちろん「もっとくれ!」ということも出来ます。美味しいので気をつけないと食べ過ぎますよ。
- あんまりのんびりしていると出入り口の扉が閉められてしまいますので注意。もっともゲストの食事の後がアシュラム職員の食事時間ですから独りで取り残されるわけではありません(食事時間に遅れたときは職員達と一緒に食べるなんて事にもなったりします)。もし出入り口の扉が閉められてしまったら、厨房を通って外に出られます。ゲストが厨房を見る機会はあまりないですから(見学は自由です)、面白かったりします。
- おなかの調子が悪いとか、あまりたくさん食べたくないというような場合は、夕食時には「フルーツ&ミルク」だけ配膳される列があるので、最初からそこへ座ります。場所的には説明しにくいですが、少し遅れ目にホールに入ると、何人かが離れたところで並んで座っているので解ります(基本的に旧食堂のラマナの祭壇の横です)。
- お茶の時間はホールは同じですが鐘の合図がありません。おおよその時間(16:00)を見計らっていけば人が並んでいるので解ります。長い行列になることもあるので早めに行った方がいいでしょう。お茶時間でのおかわりは人が多いときは断られたり、配膳する人によっては「コップを換えるように」と指示されたりします。
- 特別な儀式などの関係で食事時間が変更される場合もあります、事前に通達がありますから聞き逃さないように。ニューホール(新しいダイニングホールではなく、サマディ・ホールの隣のホールのこと)前の臨時掲示板にも載ります。また訪問客が多すぎて混雑が予想される時などはフェイントかけて?「鐘が鳴らない」のに始まる・・ということもたまにありますので要注意(笑)
- 食事料金は一食いくらと定められているわけではなく、ドネーション(寄付)となりますので、それぞれのお志で結構です(・・・・と言われるとと日本人は困りがちですよね)
参考までに、下記「アシュラムの食事に関する私的考察」というレポート記事を是非ご覧ください。
アシュラムの食事に関する私的考察→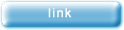
費用 について
アシュラムに滞在するためにはどのくらいの費用がかかるか?という事について説明いたします。
- たまに勘違いする人がいるのですが、だからといって「無料」でもありません。
- 要するにドネーション(寄付)ということです。この一食は、この一泊は一体「自分」にとっていかほどに相当するのか?と言う事を自分で決定することになります。難しいですよね。
- しかし最低限、現地価格での実費相当分は出すというのは当然のことでしょう。ですからインドを渡り歩いているバックパッカーなら、同じレヴェルの食事と部屋をアシュラムの外で利用した場合どのくらいになるか?は容易に見当がつくはずです。
- そうでない方の場合はインドの物価感覚自体がよく解らないでしょう。一応の目安ですがインドにいるバックパッカーたちはおおよそ一日1500円位で三食と宿代を払って生活している・・・・はずです。
- それから滞在する人の社会的地位や身分に寄ってもやはり違うはずです。インドのような国ではお金持ちはそれに見合った施しをするのが当然である、という「社会常識」があります。(お乞食さんたちもプロ意識に徹していますからそう簡単に引き下がりません。)更に厄介なことに日本社会にあってはごく普通の庶民であるはずの人も、向こうでは金持ちであると思われています。
- ドネーションはいつしてもいいのですが普通はアシュラムを出るときにします(チェックアウト時間というものは特にありません)。フライトの関係で早朝出発になる場合は前日にしておきましょう。オフィスのある建物の中に「窓口」があります、インドルピー(現地通貨)だけでなく、USドルや日本円及び世界主要通貨でも支払うことが出来、領収証を発行してくれます。領収書と一緒にカードサイズのバガヴァンの写真とビプティー(聖灰)が貰えます。
- 瞑想ホールをはじめ各ホールや、管理下にあるスカンダ・アシュラム、ビルバクシャケーブへの出入りは無料です。図書館での閲覧も無料です。以前はデポジットを払えば「借り出し」できましたが、昨今では「館内閲覧限定」となりました。
- 正門を入るとすぐ脇に履物を預ける場所があります。ここももちろん無料なのですが、たまに料金を請求してくる場合がありますが、それは係員の冗談です。ここに預けずにそこら辺に脱いでおくと泥棒さんに持っていかれたりします。履物を部屋まで持ち込むことは構いませんが、持ったままホール内を横切らないように!これは大顰蹙を買い、厳しく注意されます。部屋の外に脱いでおくと、子犬や小猿が持って行っておもちゃにされぼろぼろになることもあります。
- アシュラムにタクシーを依頼したときの支払いは到着時に運転手に直接支払います。これはインドルピーでの支払いですから、深夜着のフライトを利用して空港への出迎えを頼んでいる場合は、忘れずに空港内の銀行で両替をしておいてください。もしうっかり忘れた場合は運転手に、後日オフィスの方に支払っておくから・・・ということで話をつけてください。
- アシュラム内で外貨両替は出来ません。ティルヴァンナマライの銀行での両替はあまり便利ではなく、うっかりすると半日仕事です。外国人相手のネットカフェなどで両替可能でとてもスピーディなので便利ですが、バンクレシートは発給されない他、日本円は扱わないところも多いです。短期滞在の場合は、空港もしくは大都市の銀行や公認両替屋で事前に両替しておいても良いでしょう。
- あれこれの生活諸雑費(食事以外の飲み食いや日用品の購入、郵便、電話、インターネットなどの通信費、外に出かける場合のオートリキシャ代、諸々のお土産代などなど)、がいくらくらいかかるか?というのは人それぞれですからなんともいえませんが、タクシー代は別として100USドル分の両替でも1週間程度の短期滞在者はおそらく使い切れないだろうと思われます。
- 山歩きなどでガイドを頼むときの料金は相手との交渉です。ただし注意しないと思いっきりぼられます。因みにアシュラムには公認ガイドというものはありません、それを装う人間は要注意です。
- といった具合なので出発に当たっては、日本円のままもって行って空港で必要分をルピーに代えておく・・・ということでよいかと思います(もちろん「非常事態用」にUSドルをいくらか用意した方がいいですが)。ただしこれはアシュラム直行直帰の短期滞在の場合です。
- いずれであれアシュラム到着後は、生活諸雑費としてのルピー以外の外貨及びパスポートや航空券などの貴重品は、オフィスの金庫に預けることをお薦めします。悲しい事実ですがアシュラム内での泥棒事件は少なくありません、あろうことか瞑想ホールの中で、瞑想中にごっそりやられることもあります。バガヴァンの御前でそんなことが?と思われるでしょうが、泥棒さん達には格好の仕事場です。
訪問時期と服装
訪問時期によっての生活環境の違いを説明します。
近年では「不敬と見做されないような」常識的なマナーに則った衣服の着用が求められるようになりました。→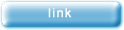
- 季節的にはおおよそ乾季・雨季・酷暑季の3シーズンに分かれます。
- タミル・ナドゥ州はベンガル湾側なのでインドのほかの州と異なり、10月中下旬から12月上中旬にかけてが雨季となります。
- 南国の雨季というと間欠的な激しいスコールを想像しますが、必ずしもそうとも限らず日本の梅雨のように一日中雨が降り続くこともあります。強い風や雷を伴うこともあります。結構肌寒く感じたりすることもありますから注意が必要です。
- この時期の滞在はまず間違いなく雨に降られます。ホールなどの床が大変滑りやすくなるので気をつけないと危ないです。
- ギリ・プラダクシナ(聖山巡回行)も雨に降られる覚悟が必要です、ずぶ濡れになるとかえって気持ちが良く、楽しく歩けたりしますけどね。
- 草木が力強く息づいているのが感じられ、大気が濃厚です。埃が洗い流されていることもあり、夜晴れたときは星空が素敵です。
- アルナーチャラが雲に隠れて姿を見せないときもあります。
- ディーパム大祭もこの時期になります。アルナーチャラの頂上に灯が入る瞬間はそれまでの雲がうそのように退いたりします、不思議ですね。
- 雨季が終わって3月中旬位までが乾季です。晴れる日が多いですが1月などは朝夜は冷えますから、風邪をひかないように。薄手のセーターがあったほうがいいでしょう、寝るときもブランケットが欲しいです。これはアシュラムの方では用意してくれませんから自分で調達する必要があります。夜の水浴びは気合を要しますよ。
- 2月下旬から3月半ばまでは暑くもなく寒くもなく気候としてはちょうどいい頃合です。訪問お薦め時期でしょう。
- 雨季の中ごろから乾季にかけてという時期は、ディーパム大祭に引き続きクリスマスがあり、更にはバガヴァンの聖誕祭があり、シヴァ・ラットリの祭りがあり・・・という具合でかなり訪問・滞在客が増えてきます。とりわけ西洋人たちはこの時期に大挙してやってくる傾向があり、外のゲストハウスも混み合います。外国人目当ての商売も繁盛しています。というわけで12月から2月にかけては結構わさわさしているので、静かな環境を求めたい方にはあまりお薦めできないかもしれません。
- 3月下旬になると結構暑くなってきます。4月以降は日本の「真夏」の感じとなり6月半ば頃までが酷暑季です。
- 読んで字のごとく、これはもうべらぼうに暑いです。とりわけ5月は死にそうに暑いです。アシュラムにはクーラーはありません。ゲストルームにも扇風機があるだけです。しかもこの時期やたら「停電」が多くなります。しかも一番扇風機が欲しい昼ごろに「停電」したりします。
- 部屋の壁自体が熱を持ってきます、ゲストルームの位置によっては西日にさらされます、水すらも生温くなっています。ベッドマットの綿自体が暑くなってますから、到底そのままそこでは寝られません。床にござを敷いて寝るとか、蚊帳を用意して外で寝たりします。
- 裸足で歩かねばならない場所で屋外の部分(特にサマデイ・ホールからダイニング・ホールの間)などは、まさしく「飛び跳ねる」感じでなくては火傷しますよ。
- という具合なので初めて訪問する方や暑さが苦手な方にはあまりお薦めできません。ただしそんなわけですから訪問・滞在客が減りますので、実は一番「静かな」時期だったりします、外国人がかなり減るので彼ら目当ての商売の店は営業時間短縮とか完全に閉店してしまうところもあります。
- もうこれは勘弁してくれ・・・というくらい暑いので外を出歩くときは「熱射病」にかからないように十分注意してください。無理をするとヘタリます。インドの太陽の苛烈さに逆らってはいけません。
- とはいえ「北インド」の酷暑季(体感温度50度!)に比べればまだましな感じがします。日陰で風通しの良いところにいる分にはどうにかしのげたりします。更にはここ数年の日本の夏の猛暑に比べますと、湿気がない分幾分まし・・・かもしれません。
- バガヴァンの命日の法要はこの時期にあたります。参加する方はそれなりの覚悟が必要かもしれませんね。
- 乾いているので埃が多くなります。人から水をもらえない野生の草木はヘロヘロになっています。雨季に充分な雨が降らないとこの時期に水不足状態になることがあります。アシュラムでも状況によっては給水車を呼んで、「水を買う」こともあります。あまりに深刻な場合は、ゲストの受け入れ中止となる場合も過去にあったそうです。
- 7月に入りますとだんだん暑さも収まり始めます。アラビア海側のケーララ州は雨季に入りますので、この雨雲がこちらの方にも時々やってくると夕立になったりして気持ちの良いスコールをもたらしてくれます。「ケーララの貰い雨」と呼んだりします。結構強く降る事もあり、ヘタっていた草木が息を吹き返し埃が洗い流されて、すかすがしい気持ちになります。赤茶けていた御山が緑っぽくなってきたりします。
- この時期にはバガヴァンの母堂の命日の法要がありますが(タミル暦計算により日付が異なる)、これはさほど混み合うことは無いようです。有名な牛「ラクシュミー」の命日もこの時期になります。
- 7月から9月にかけてというのは気候的にはもっとも過ごしやすいのではないか・・・と思われます。しかも7・8月は特に大きな行事もないので(9月はNavaratri の祭りがある年もある)、意外と空いていたりして「滞在の延長」が認められたりもします。そしてこの時期は日本人が増えてきます。夏休みということで時間が取りやすいからでしょう、ちなみに日本からのチケット代もピークシーズンの前後は一番安くなる傾向がありますから、夏休み・盆休みをずらして取ることが出来る人はこの時期の滞在がベストかもしれませんね。
- 服装については特別な規定はありません。皆ばらばらです、儀式への参加に当たっても特別な服装でなくてはならないということはなく、普段着のままでも問題はありません。暑いこともあり男性はTシャツ・短パン、上半身裸なんて人も見受けられますが、以前は大目に見られていたものの最近はドレスコードに抵触するようですので、避けた方が賢明でしょう。
- 特にあまりに「珍妙」な格好(いわゆる「ヒッピー崩れ」のような)をしていると良くは思われません。長期滞在を試みたい人は当然こういう点も「人物評価」の対象になるでしょう。男女ともそれらしいインド服が無難です。
- 靴は滞在中は不便なだけです。靴下も冬の時期にホールなどではあったほうがいいですが、履物を脱がなければならないところは建物の外にもあるので汚れることになります。
- そんなわけで素足に草履、できればアシュラム内は裸足で通してしまう方が楽です。ちなみにギリ・プラダクシナ(聖山巡回行)も全行程「裸足」で歩くのが「本義」です。
- ところがアルナーチャラ山自体は履物を履いて歩いても構いません(出物腫れ物ところ構わず、おしっこその他を御山でしても問題はありません)。棘のある潅木が多いのでその方が安全です。もちろん裸足で歩いた方が気持ちがいいことはいうまでもありませんが。インドの聖地における聖穢の観念は必ずしも日本の神道の感覚と同じでありません。
参考までに、下記「アシュラムのドレスコード他に関する補足説明&私的考察」というレポート記事を是非ご覧ください。
アシュラムのドレスコード他に関する補足説明&私的考察→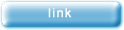
次はアシュラム行事あれこれの紹介コーナーです
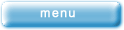 ←目次に戻る
←目次に戻る
前の記事に戻る→ 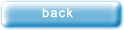
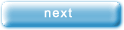 ←次の記事に進む
←次の記事に進む