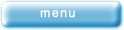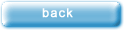余はいかにしてラマナ信奉者となりしか? その6
かくして97年3月(の1日だったように記憶している)に柳田先生は帰国の途につかれ、私は柳田先生の現地住居(「Arul Ramana」・・通称ヤナギダハウス)の留守番屋という日々を送り始めることになった。
前号で紹介したように、このヤナギダハウスは先生が建築費をドネーションして(存命中は先生の専用住居として使用する約款の元に)アシュラムの飛び地領の中に建造され、アシュラムが所有・管理する不動産物件なのであった。
2階建ての簡素な建物ではあったが、1階には先生の書斎兼居室の他にリビングルーム・冷蔵庫と湯沸かしポットを備えたキッチン(自炊ではなかったのでコンロは無し)・ホットシャワー機器装備の浴室・インド式トイレ・そして狭いながらも簡素な祭壇を備えた瞑想スペースまであり、
また広い2階ベランダには屋根が掛かっていて雨天でも洗濯物を干すことが出来たし、日差しを遮ってくれるのでアーサナなどの身体的エキササイズの実施にももってこいの空間であった他、更に屋上へと外階段を上るとそこはアルナーチャラの威容を目の当たりに拝することができる絶景ポイントなのであった・・99年のディーパム聖火はここから拝んだのだが、その「たった独りしかいない絶景空間で聖火と対峙した」・・のは今となっては得難き体験であった。
(先生が逝去された04年8月以降は、この建物はかってのリビングルームにも複数台のベッドが置かれてアシュラムの「家族・グループ用」ゲストハウスとして運用されるようになった・・・圧倒的なインパクトがあった屋上からの眺望は、敷地内外周辺の木立が生育繁茂して視界を遮るようになってしまい、残念ながら現在にあってはアルナーチャラを臨む絶景ポイントではなくなってしまった。)
そして当時その2階はシングル・ゲストルーム(洋式トイレ・シャワー付き、ただしホットシャワー機器は無し)になっていて、そこには「先生が許可した者」だけが宿泊できたわけだが、前号にも書いたようにそれは同時にラマナアシュラムのゲストとして承認され、アシュラム食堂で食事(朝昼晩&お茶の時間)をいただける・・ことを意味していた。
(これは当時いかに先生がアシュラムから絶大な信頼を寄せられていたか?・・の証左ともいえるだろう)。
でまあ私はそこの「留守番屋」として、先生が再び戻られるまでの間は「好きなだけそこに滞在してもよい」・・ということになったわけだが、つまりそれはある意味で「アシュラムへの無制限滞在許可」を得たに等しい立場?に置かれたわけでもある(・・しかも設備的には「スペシャル・ゲストルーム」である!)
後にはシュンニャさん(パパジ「真理のみ」翻訳者の崎山綾子氏)もこの役を担うことになり、彼女が居住していた期間に先生が逝去されたため、「留守番屋」としてこの建物での長期滞在を経験したのは結果的に我々2人だけとなった。
全くこれは不思議なご縁と成り行きなのであるが、それにしてもなぜ私のような変梃な野郎・・・到底まじめな信奉者らしからぬ言動・立ち振る舞いが目立つこの私(現在も大して変わらない・・笑)が、ラマナアシュラムでの「無制限滞在許可」に等しい待遇に巻き込まれた?(実際この表現が妥当なのだ)のであろうか?
・・と常々考えてみるのだが、未だにわからないままである・・多分それが「今生における私の運命」なのだろう、としか言いようがあるまい。
もっともその体験があればこそ、以来ほぼ毎年数ヶ月単位でのアルナーチャラ訪問・滞在を繰り返すことになり、その間の様々な蓄積がやがて「臨在サイト」立ち上げ・管理運営へと結実していったわけである。
このエッセイシリーズは題名が示唆するように、ラマナ信奉者であると「恒常的に自覚するようになっていった」プロセスの記述をメインモチーフとして構成し、あれこれの出来事を順次書き綴っていこう・・という趣旨なのだが、
ということは当然ながらその前段階として「全然信奉心のない」者という段階から始まったわけで(笑)、ジッドウ・クリシュナムルティに過分に影響をうけ、スピリチュアルな領域の中で生起するあれこれの事象について、常に「懐疑的」であることを旨としている私(現在も然り)にしてみれば、
ラマナの教えにおけるジュニャーナとしての営為にはそれなりの共通項を見い出せていたにしても(あくまでもそれは「知的理解」でしかないが)、バクティという「信仰的な営為」には結構心理的な抵抗が大きくて、
この「留守番屋」生活が始まった当時はラマナに、ましてや山としてのアルナーチャラには、「全くと言っていいほど信奉心を持ってはいなかった」・・・と言っても過言ではない(ギリプラダクシナにしたって、正直なところ「こんな面倒なことやってられんわい!と感じていたし・・)。
そもそもその1年前のアルナーチャラ初訪問にしても、前々から憧れていて機会を待って準備していたわけではなく、旅の途上「ふと思い立って」やってきた・・に過ぎなかったし、この97年の訪問にしても「エッセイその4」に書いたように晴天の霹靂的な成り行きで急転直下に実現したものであった。
そしてどちらかと言えばバックパッカー的な感覚の延長線上のまま、全く予期していなかったアルナーチャラの長期滞在(しかも「アシュラム・ゲスト」として!)生活を送ることになったわけである・・・ということ自体が既にラマナ=アルナーチャラの比類無き臨在と恩寵の顕現以外の何ものでもないのだが、そのことを真摯に「自覚」出来るようになった・・のはもっと後のことなのである(笑)
これでもしラマナアシュラムが一般的なヨーガアシュラムやスピ系ワークショップやリトリートのように、
「あれこれのレクチャーやらセミナーやらエキササイズなどによって構成されたシステマティックな『修行プログラム』があって、そういうものの『3ヶ月コース』を受講する」というような明確な目的の上での滞在生活を送る・・
なんて具合であったならば、それなりになかなか「楽しい・充実した」日々であったかもしれないのだが、臨在サイトでの説明&ブログ記事などで繰り返し紹介しているように、ラマナアシュラムではそのようなカリキュラムは一切存在しないのである。
これは実際問題としてなかなか困惑したりもする・・ある時などは訪問したヨーガの先生から「すいません、ここでは『何をしていれば良い』のでしょうか?」と真剣に質問されたことすらある・・・
もちろん「真面目な修行者」として堅固な意志&各個の資質に適したルーティン・ワークが確立しているような境涯に在る者・・ならば、サーダナに専心することに何らの疑問も躊躇も違和感もなく適合できることだろうが、しかしそれを「長期滞在」という時間軸に於いてどこまで鍛度を高く保ち続けられるか?・・は案外大変なことであろう。
アルナーチャラの元でのサーダナとは、例えば永平寺の雲水修行のようなハードな形態とは正反対なゆるさ・自由度の元に生活が繰り返されるのだが(笑)、しかし直面・対峙せざるを得ない「実存状況」はかなりの峻厳さなのである・・日常生活の刻々の局面に於いて、もっとも根源的・本質的な「私は誰か?」の命題が、「常に鼻先に突きつけられる」ことになるのだから。
・・・というような生活空間の中に、私のような不真面目かついい加減な「半ちく野郎」が放り込まれてしまったのである(笑)、いったいその当時の私はどのような心境で「留守番屋」生活を送っていたのか?
私の書いているブログは臨在サイト立ち上げ時にスタートしたものなので、この「留守番屋」時代のまとまった記録としての日記などはないのだが、唯一の資料として日本ラマナ協会会報の「会員便り」のコーナーに、当時先生から勧められて寄稿したエッセイ?が残されているので、次回はその文章を復刻掲載して紹介したいと思う。

2004年撮影時の「Arul Ramana」・・通称ヤナギダハウス、その敷地の半分は牛に食べさせる牧草の畑となっていて、この畑への水やりを一時期私が担当していたりもした(笑)

2013年撮影の「Arul Ramana」・・通称ヤナギダハウス(左側)、敷地内の牧草畑が無くなり職員住宅が建造されている。
次回に続く。
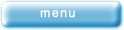 ←目次に戻る
←目次に戻る
前のファイルに戻る→ 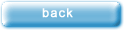
 ←次のファイルに進む
←次のファイルに進む