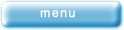 ←目次に戻る
←目次に戻る余はいかにしてラマナ信奉者となりしか? その7
前号で書いたようにこの「留守番屋」時代には、「滞在日記」的なまとまった記録は全く書き残していないのだが、当時の日本ラマナ協会機関誌(年4回発刊)の「会員便り」に寄稿した文章があり、今となっては唯一の残存資料である。
これは99年1月15日発行号に掲載されたもので、実際に原稿を書いたのは98年の夏~秋頃であり、文中にも出てくるが「2度目の留守番屋」の時の記述である。
98年は7月下旬~9月中旬と11月末~明けて99年1月初頭の2期に分かれての滞在だったのだが、機関誌の発行時期から逆算すると「前期」滞在時での執筆だったかな?・・と考えられる。
(因みにこの年の滞在が2期に分かれた経緯・・・というのもなかなか面白いエピソードを含んでいるので、いずれここで紹介する予定である。)
というわけで能書きはこの辺にして当時の文章を紹介しよう・・・ほんの僅かの「ウェブ公開には差し障りのある」部分を削除したが(笑)、ほぼ全文そのままの復刻である。
>>>>>>>>
「ある長期滞在者の反逆的手記」
「じゃ、よろしく」「はあ・・」という具合でY先生はタクシーに乗ってすたたたた・・・と去っていった。かくして私のArul Ramana 留守番の日々が始まった。これが2回目だ。私がアシュラムを訪ねる時期というのは何故かY先生の帰国する頃にあたってしまい、「鈴木さん、どうせヒマでしょ?」「はあ・・」という具合丸め込まれ、結局留守番するはめになってしまうのだ。
アシュラムを訪れる日本人、特に協会会員はたいへん歓迎されている。熱心なディヴォーティである上に、ほとんどの人たちは社会的にまっとうな職業人で、短期滞在のわりにはたくさんドネーションしてくれる。
かくして私のような不熱心・非まじめな長期滞在者は、あまり歓迎されていないのではないだろうか。懐疑的不可知論的無神論者のうえに、40歳近くなるというのに住所不定無職で貧乏だ。具合の悪いことに外国語をさっぱり解さない・・・が故に正体不明・謎の人物なのだ。
アシュラムと周辺のインド人たちは私をY先生の「息子」「秘書」「弟子」「召使」「用心棒」etc.と、それぞれ勝手に思いこんでいる。そんな私がアシュラムでのうのうとメシを食っていられるのは、もちろんY先生のご威光のおかげだ。
不熱心・非まじめ長期滞在者の私はあえて反逆的声明をする。
「ここに長くいると、いいかげんたいくつで嫌になってくるぜ!」
旅が面白いのは、それが非日常的状況だからなのだ。長期滞在というのはこれは日常的生活である。日常生活に特別な感激なんかあるわけはない。大体、「何も特別なことは起こらない」のがアルナーチャラだと思う。
朝起きれば山がある。飯を食えば山、瞑想すれば山、アーサナすれば山、太極拳すれば山、気功すれば山、お茶のめば山、散歩すれば山、小便すれば山、糞すれば山、水浴すれば山、洗濯すれば山、本読めば山、手紙書けば山、思索すれば山、ぼけっとすれば山、歯みがきすれば山、寝れば山、「私」がいれば山、迷っていても山・・・という生活が毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日・・・続く。
どこにも面白いことなんかないぞ。一体ここにこれ以外の何があるのか?一日24h四六時中ただひたすら山山山山山山山・・・。
このあきあきする超うんざりのたいくつさが、私とアルナーチャラが直接向かい合う状況を嫌というほど提供してくれるのだ。
さあ、そこで何を問うのか?
私は「真我の探究」なんかしていない。大体「私は誰か」なんて問う以前に、そもそも「私」って何なのだ? そもそも「真我」って何のことなのだ? 「アートマン」にしろ、「ブラフマン」にしろ、「神」にしろ「グル」にしろ大体そもそもそれは一体何なのだ? どういうことなのか私には理解できない。誰か答えてくれ、「思考」って何? 「世界」って何? 「在る」ってどういうことなのだ? 「無い」ってどういうことなのだ?
賢明な諸氏は言う。「君、それは君のEGOの想念だよ」
わかってるわい! ただその「EGO」って何? 「想念」って何なのだ? 一体全体このどたばたしたこの一切合切がそこにそのようにそうしている・・・ということ自体、つまりそれはどういうことなのか? そしてそれを問う「私」は誰ざんしょ?
バガヴァンは「沈黙の教え」の人だから、肉体の有無は関係ない。「本尊」のいないアシュラムに答えてくれる人はなく、かわりにわんさとバガヴァンの写真がある。無意味な肉体のしかもコピーにすぎぬ写真に「ありがたい力」なんかあるわけない。ただ効用はある。バガヴァンはいつもカメラ目線で写っている。だから必ずこちらを見つめている。そうするとふっと彼の声を聞く錯覚に陥る。
「君はアホか? 考えたってしょうがないざんしょ? 肝心なのはリアライズ(直接体験理解)なんだよ~ん!」
とバガヴァンが語りかけてくれるわけだ。
「はあ・・しかし一体私はここで何してるんでしょうか?」「わかってりやここに居る必要はないざんしょ?」「はあ・・左様ですかあ・・」
という具合だ。
うーむ、そうなのだ。わかんねえからここに居るんだよなあ。答えはすべて山にある。この太古からあるらしい、まるで天から降ってきてそこへ鎮座してしまった地球外超絶知性体の擬態のように、いかにも「とってつけた」如く、アルナーチャラはそこに在る(P.K.ディックの『ヴァリス』を参照されたし)。
へっ、こうなった日にゃあ何がどうだっていいやんけ! そこにどかっと山があるんだから、今さら何に文句をつけようてんでぃ! と開きなおる私に、アルナーチャラはただ沈黙の笑いを返すだけである。
でもこの山のすごいのは、こっちのどたばたにおかまいなく、ギリプラダクシナしようがしまいが、
(しかし”ギリプラのY”と呼ばれる家主に、「鈴木さん、ギリプラダクシナはいいですよ・・」と鍛えぬいた”青年のような神々しい脚”(これが70代老人の脚か?)をこれ見よがしにみせつけながら、ニコニコ、ボソボソ言われると、居候としては「はあ、そうですねえ・・」と義理プラダクシナをやらねばならん。)
じわじわじわじわじわ・・と放射能の如く、”魂の肝心なところ”に直接浸透してくることなのだ。もちろん何も起こらない。起こるわけはない。「恩寵」なんぞくそくらえ!である・・・のだが。
じつは後々になってからわかるのだ。日本へ戻ってきて、すっかり忘れた頃にひょっこり「こんちわ、お元気ざんすかあ?」「うぎゃあ、アルナーチャラやんけ!」なんていう事態がよくあることは事実である。
本当はこの山は、「ぐははは・・・」と「恩寵」をぶちまけ続けているが、それにこっちがいつ気づくか?ということなのだ。
かくして、たいくつでしかたないのだが、じゃ逃げ出してどこぞへ出かけよう!という気力もやる気もなくすようにできていて、ただただじ~っと山に向かい合ったまま、ひたすらY先生が帰ってくるのを待つわけである。そして帰ってきた先生はきっとこう言うのだ。
「で、鈴木さん、来年はいつ来るんですか? 私の予定は・・」「はあ、左様ですか」
ありやりやりゃ、また留守番させるつもりだな。結局そうなってしまうに決まっている。一度アルナーチャラにとらえられたら絶対に逃げられんのだそうだ。大体Y先生自体、人の姿をした「山の使い」として私の前に出現しているに違いない。どうせならじじぃじゃなくて美しい若い娘の姿で現れてくれたほうが楽しい(す、すみませんっ!!)。
まったくなんとも恐ろしや、ああアルナーチャラ・・である。それにしても、ところで一体アルナーチャラってそもそも何なのだ?・・・と「ウソつきヨーガ屋」は今日も山に問うのだった。
鈴木尚志(住所不定無職、一応「うそつき」Yogaてぃーちゃあ)
☆日本ラマナ協会会報第34号(99年1月15日発行)、「会員便り」より転載
<<<<<<<<<<<<<
という具合である・・・これを書いてから18年になりなんとしているわけで、今回あらためて読み返してみると「若気の至り的(とはいえ37才であったが)な畏れを知らぬ勢いの書きっぷり」で、各所各所で「顔から火がでる」思いではある(笑)
こんな「ぶっ飛んだ?」文章は協会機関誌始まって以来だったのはもちろんであり、私の「異質・異端」ぶりが如実に現れているのだが、これを掲載するにあたり当然柳田先生も事前に目を通されていて、一切の「削除」「訂正」「書き直し」などは要求されずに掲載に至っている・・・のは、柳田先生の「懐の深さ」を如実に示している好例であろう。
しかしながら、現在の私が書くブログ記事や「ラマナ・ミーティング」で喋ったりする内容の基本的骨子とでもいうようなものは、案外この文章で表現しているものと「さほど変わっていない」・・・ような印象もある、実際に「ギリプラダクシナを熱心に実行するようになった」&「ご案内業務が増えた」という点以外では、現在のアシュラム滞在時の様子も同じような感じだったりするし(笑)。
もっともまだこの頃にはギリプラダクシナもほとんどやってなかったし、バクタとして自覚も希薄であり、アルナーチャラの臨在と恩寵の「畏れおおさ」というものに関して、決して直接体験的から把握していたわけでもない。
文中にて、「ありやりやりゃ、また留守番させるつもりだな。結局そうなってしまうに決まっている。一度アルナーチャラにとらえられたら絶対に逃げられんのだそうだ。」と書いているが、
その言葉を正しく実感したのはこの文章を書いた後の、やはり想定外の成り行きで98年の2期目の滞在にいたる・・・際のエピソードになるわけで、次回はその辺を書く予定。
次回に続く。