クール・アーナンダ体験・・「醒めたる静謐なる喜び」
私は若い時分には「演劇青年」で、浜松の老舗のセミプロ劇団で俳優としての訓練を受けギャラをもらう仕事もしたし、自分が率いる表現グループでの活動も展開してきたのだが、結局のところ残念ながら「自己陶酔・自己満足」のレベルから脱却できなかった(笑)。
そして1990年以降インドに行くようになってからは、「霊性の道」が人生のアプローチのメイン命題になった・・わけで、早い話が「挫折した演劇中高年」であるのだが、2006年からTAICHI-KIKAKUというパフォーマンスグループとのご縁が出来て、2008年からはこのグループの「身体詩劇公演」での「サブ・パフォーマー」として再び舞台での表現活動を再開し、2014年5月には韓国・春川で挙行された「国際演劇祭」にグループが招聘された際に、私も公演出演者の一人として連れて行って頂いたのであった。

参加していたポーランド・イラン・ロシアそして韓国の劇団の公演を観劇したりもして、どの舞台も俳優たちの身体表現レベルが極めて高度で素敵にアバンギャルドなパフォーマンスであったし、何よりもそれらが展開されている同じ国際演劇祭のステージに、自分も劇団メンバーの一員として参加しているのだ!!ということの感激。
・・かって夢想していた、パフォーマーとしての「評価の高いレベル」での活動のその末席に自分がいる・・・ということに、ある種の感慨が去来したわけである。
そして実はこの時に、「(プチ)覚醒体験」と呼べるであろう不可思議な体験があった。
もっともその体験が起きたのは公演中の舞台上という特殊な時空の中ではなく、場所柄としては「特別な聖地」でもなければ、何か特別な行為(瞑想だの行法などの)をしていたわけではなく、
公演日程を全て終了してソウルに戻り、金浦空港にて羽田への帰国便を待合い中の、
「空港の一角にあるレストランで、皆と食事をしていた時」
・・・だったのである。
それは全く予期することもなく「不意にやってきた」のであった。
仲間たちと食事をしながらあれやこれやと雑談をしていたのだが、なぜか唐突に、
自分の周囲の光景から、事物・事象それぞれの「意味」が「ただ流れていく」という感覚
・・・がもたらされたのである。
それはかってタイ・パンガン島でのドラッグ体験の一環として体験した「意味消失」に似ているものの、その時と異なるのは・・・
記号としての名称が消え去るのではなく、どこにも引っかからず・内容が「生成発展せず」、ただそのままで「意味が流れ行く」のを一切の「判断・解釈」なしに「ただそれを冷徹に見つめている」感じ。
流れ行くそれらの事象を「一切の感傷なし」でただ「見送っている」ような感じ・・例えば食事に同席している仲間の女性たちの美貌を眼前にし、その「美」それ自体は感じつつも、それらに対する諸々の「個人的な情動的反応」が希薄もしくは全く生起してこない、とでも言おうか(その中の一人には当時熱っぽい「恋心」さえ抱いていた・・にも関わらず)。
そしてそのような「判断停止的」状態でありながら、入眠時のように朦朧・麻痺しているのではなく、意識はしっかり覚醒して機能しつつも、それに対して「個人的な反射的反応、悲しい・寂しい・嬉しい・羨ましい・・などというような、あらゆる喜怒哀楽の感情や想念の波が全く起きてこない「ベタなぎの湖面」のように鎮静・透徹している「虚空蒼茫碧宙」にあって「則天去私絶無爽快」とでもいおうか?
これが表現過剰だとしたら、少なくとも瞬間「感情が生起する」にしても、それが殆ど粘着することなくさらさらと「流れ去っていく」・・という表現の方がより適切であるのかもしれない。
例えばそれは何かに集中している時の「内的静寂」に近似しているのではあるが、ただし集中時と違って「周囲の状況」は俯瞰的に全部関知し得ている・・という違いがあるとでも言えるだろうか?
実際その最中にあっても人との会話はしっかりと普通に成立していたし(だから「忘我」状態ではない)、おそらく同席していた仲間たちは、その時私がそのような「特殊な意識状態」の渦中にあった・・とは気がつくことはなかったであろう。
・・・これはある種の「瞑想状態」であり、あるいはプチ「覚醒」状態の一様相と言い得るだろうし、あるいはこれがヨーガ・スートラ第1章冒頭の記述であるところの、
「ヨーガの目的は『心(想念・マインド)の働き』を停止させることである」
というものにあたる・・のかもしれない。
そして何かしらオルタナティブな変性意識状態というか、いわゆる「サット・チット・アーナンダ」状態、「心をかき乱されない平静・平穏」というシャンティさをアーナンダの発露とするならば、
「神様酔い」や「麻薬的融解感」としての半ば神経回路系身体感覚的な『至福』感とはまた別物の、何というかこれは「醒めたる(クールな)静謐なる喜び」というようなアーナンダ?・・・なのかもしれない。
例によってこれを「音楽」として表現すると
バッハの鍵盤音楽作品群というのがそれに最も近似している・・・ように感じられ、私には「絶対調和宇宙の形而上学的音楽」と評するに相応しいインプレッションが想起されてならない。
表象としてのラマナ=アルナーチャラ」抜きでの体験
そしてこの体験の特徴としては、それが「表象としてのラマナ=アルナーチャラ」抜きでのものであった・・・ということでもある。
前々回のエッセイで紹介した「刃傷事件」では「プチ臨死体験」のプロセスにおいて「ラマナ=アルナーチャラ」のヴィジョンが鮮明に去来したし、前回紹介した「南無大師遍照金剛」体験ではそれが起きたのは「ラマナの聖廟をプラダクシナしている」最中であった・・・わけだが、
この体験では場所も無縁だし、「お姿としての」ヴィジョンは全く出現していないのである。
もっとも公演期間中は春川市の中心である小高い山のすぐ近くに我々は滞在していたのだが、暇なときに湖の方に散歩しながらその山を見たらお姿がアルナーチャラによく似ていて、思わぬところでアルナーチャラにお会いしたようで何だか嬉しかった!・・・ということはあった。
なのでこの体験が、そのアルナーチャラそっくりのお山を前にして瞑想していたら・・・だったなら、「アルナーチャラのお姿を想起する」という心理的な瞑想テクニックによって、そのような「変性意識体験」が招来した・・・という具合に説明も出来ようが、
この体験が訪れたのは前述したように、
金浦空港にて羽田への帰国便を待合い中の、「空港の一角にあるレストランで、皆と食事をしていた時」
・・・だったわけで、お姿としての・表象としての「ラマナ=アルナーチャラ」は全く登場してこなかったわけである。
しかしながらこの体験の本質はやはり、「真我であり・サットグルでもある」ラマナ=アルナーチャラの比類無き臨在と恩寵そのもの・・としか私には考えがたいわけでもあり、
むしろ逆に、どこに行ったとしても「サットグルは常に臨在しおわしまするのだ!!」ということ。
たとえ「ただ独り在る孤高」モードにあってもそれは決して「閉鎖的孤立」ではなく、常に「同行二人」ということであって「サットグルの時空に制限されない臨在」ということをリアルに感得した事柄だった・・といえるだろう。
もっとも時間が経過してから突然・・というあたりが、やはり実は「効き目が遅い」という評判のある?アルナーチャラらしいではないか!(笑)
かくしてこの体験は、「刃傷事件」と「南無大師遍照金剛」体験と並ぶ、個人史上の「霊性の道」におけるエポックメイキングな体験と評してもよいのでは?・・と感じつつも、一方でその時点にあっては前2者のような直感的な「絶対的な確信」というだけのレベルには至らなかった。
このような現象・体験は「徹底的に懐疑する」ことが望ましいわけで、もしそれが真に「覚醒(プチではあるにしても)」体験ならば、それは出来事としての「新たなる地平を拓く」という水平軸の展開だけではなく、垂直軸上の「質的変容」がもたらされる可能性・・であるはずなのだが、
さてこの体験から5年が経過した現在の時点であらためて振り返ってみると・・・?
やはり実際問題としてこの体験以来、生活の様々なフェイズにてこれまでとは異なるあれこれが生起するようになった・・・とは言えるようだ。
前述のバッハについてもそれ以前はさほど興味の対象ではなかったのが、この時期から熱心に聴き始めるようになった・・ということもその一例だし、これまで煩悶してきた「某おねーさんに対する熱い想い」がするすると下降してしまった(笑)・・だけでなく、
自分を取り巻く周囲の環境にたいする「過剰な思い入れ」や「執着」などなどが、次第にエネルギーを消失して「落ち始め」、以前のように「ひりひりと渇望・懊悩する」ことが実感として希薄になってきた・・・のは事実である(まあ、単純に「年齢を重ねて枯れてきた」結果でもあるにしても)。
そして時系列で見ればこの「クール・アーナンダ」体験以降、臨在サイトでは「ギリプラダクシナ」解説コーナーを制作・掲載した他、
ONBSRASコーナーの第1部「肉体無きサットグルの臨在と恩寵」の制作・掲載という流れを加速することになった・・・わけでもある。
「バクティ」に対する多面的視座
そしてまた「バクティ」ということについて、ここ数年の間にいわば「多面的視座」とでもいうような見地を拓きつつある・・・とも言い得る感じなのではある。
敢えてキャッチコピー的にそれを無理矢理まとめると、「氷漬けにされた情熱」・・・とでも言おうか?
これはそもそも音楽評論家の故・宇野功芳氏が巨匠指揮者のオットー・クレンペラーの演奏を評して掲げた形容句なのであるが、今回の「クール・アーナンダ」そしていわば「冷徹なる(透徹した)バクティ」というある種の形容矛盾的様態をなかなか印象的に表現している・・・と言えよう。
この辺りはいずれ機会をみて、「移ろいゆく事象とリアリティ・存在の根元の考察&クレンペラーの音楽がもたらすもの、そして跳梁する道化」という一文を執筆したいものだ・・・と以前から構想中であるが、この「クレンペラーの演奏」については、ドイツ文学者の喜多尾道冬氏がなかなか感動的な文章を書いているので、興味のある方はこちらをどうぞ!
そしてONBSRASコーナー第2部としての、「バクティと信奉心、そして明け渡し」という論考シリーズにも、そろそろ着手すべき時期が到来しつつあるのでは?・・・という予兆のあれこれが現出し始めている昨今なのであった。
「安禅不必須山水(安禅必ずしも山水をもちいず)」
「禅定にあたっては、深山幽谷のような静かな環境・あるいは専門道場のような環境が必ずしも必要というわけではない」
という内容の禅語である(もっとも有名なのは、この句を受けての対句である「心頭滅却すれば火また自ずから涼し」の方であろうが)。
この「クール・アーナンダ体験」もそれがもたらされた環境・・・「金浦空港で待ち合わせ中での仲間との会食の時」という状況での体験も、この
「安禅不必須山水」を証するものであろう。
そして今回の記事では「表象無き・・・」ということで、敢えてラマナ・アルナーチャラのお写真を載せなかったわけだが、少々画面が寂しいので(笑)何かテーマに相応しい画像はないかなあ・・・と思いついたのがこちら。

皆様ご存じの「鎌倉・高徳院の大仏様」である。
昨今鎌倉方面は観光客・修学旅行・遠足・外国人・・・で、平日ですら随分な賑わいのただ中にあり、この「高徳院の大仏さん」もまた然り・・・土日祝ともなれば、長谷駅からの参道は「満月のギリプラダクシナか?」というような喧噪ですらある。
しかしその喧噪のど真ん中にあっても、大仏さんはぽかっと開けた碧空を背景に静かに端座して瞑想されている・・のだ、境内だけでなく胎内までわさわさとひっきりなしに見物客が出入りしている(20円で胎内見学可能なのだ)のに関わらず・・・である。
そして賑々しい境内の片隅でぼんやり座っていると、こちらにも確かに「禅定中の仏様の波動」がひしひしと伝わってくる・・・。
(まだ参拝されたことのない方は是非どうぞ!)
おお、これぞまさしく「安禅不必須山水」ではないか、わはははは・・・・・!!
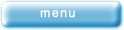
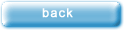
 ←次のファイルに進む
←次のファイルに進む