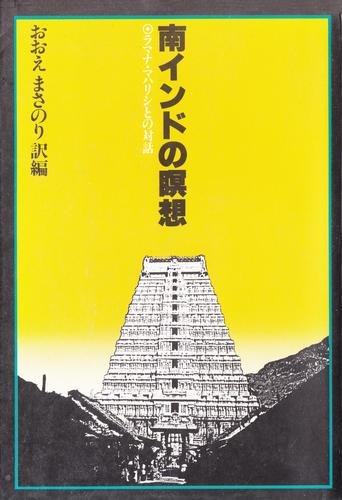
日本でのラマナ紹介の歴史における、80年代初頭の「純粋なる熱意のオーバーラン」?
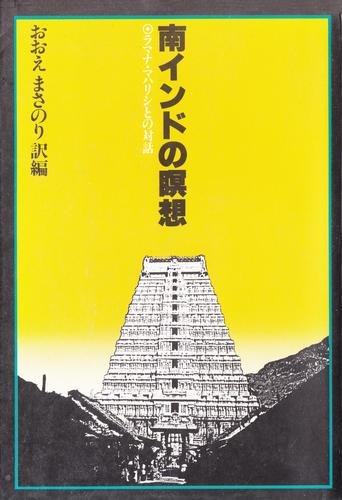
現在までに翻訳出版された「ラマナ関連書籍」は全部で10冊であるが、この「南インドの瞑想」は80年代前半に出版された・・・同じ頃にめるくまーる社から刊行された「ラマナ・マハリシの教え」(山尾三省氏翻訳)と共に、
それまで「ごくごく一部のかなり限られた人たち(例えば故・佐保田先生の指導する「日本ヨーガ道禅友会」の機関紙創刊号(73年)で紹介されているので、そこの系列のヨーガの先生たちなど・・他には山田孝男氏や橋本創造氏らの指導する瞑想グループなど)」しか知ることがなかったラマナ・マハルシという存在を、80年代辺りから台頭し始めた「ニューエイジ」思想に共振する人たち・・に広く知らしむる端緒となった書籍である。
現在50代以上の世代にとっては、この書籍によってラマナを知った人達は相当数にのぼるであろう(・・サイト管理人もその一人である)。
しかしながらこの「南インドの瞑想」という書籍はその後「ちょっと不幸な運命」を辿る事になる。
先ずは版元である「大陸書房」の倒産、その結果多くの再販希望があったにも関わらず実現しなかった・・ということもあって現在絶版、そしてかなりの高価格で取引されてきた。そしてさらに不幸なことには、日本ラマナ協会会長であった故・柳田侃先生があまりこの本に関して好意的ではなかったということ。
・・・実際この書籍には、かなり「問題がある」のである。
一つには、「ラマナ・アシュラムに許可を得ず発刊してしまった(らしい)」ということ。
日本で翻訳出版されているその他の「ラマナ関連書籍」は、基本原則としてアシュラムが著作権を有する原本(英語版)から、「翻訳者がそのまま手を加えずに」正式な許可を得て刊行されたもの・・であるのだが、「南インドの瞑想」は、おおえ氏が「独自の意図に基づいて」編集した内容なのである。
(2014年発刊の「アルナーチャラ・ラマナ 愛と明け渡し」も同様に「独自の意図に基づいて」編集した内容であるが、アシュラムの承認を得て制作されたものである)
3つのパートに分かれているのだが、1つ目と3つ目は後年になってそれを引用してきた原本自体が正式に翻訳出版された。
(1つ目は「沈黙の聖者ラマナ・マハルシ その生涯と教え」、 3つ目は「ラマナ・マハルシの言葉」及び「ラマナ・マハルシとの対話・第3巻」に収録されている)
そして一番肝心な2番目のパートというのが、「TALKS」からの抜粋引用であるが故に、資料として「最大限の価値」があったわけでもある。
・・・ただしその抜粋・引用が例えば「任意の章丸ごと」ではないため、どうしてもおおえ氏個人の意向というバイアスがかかってしまう・・というのが、ラマナの教えの紹介には大変厳格で情熱を傾けていた柳田先生としては「評価できない」理由だったそうだ(先生は「学者」でもあったから)。
以下 柳田文献より抜粋引用
しかしアシュラムを訪れておびただしい現地語や英語の書物やラマナの写真を見、現地の人々と接触するにつれ、「南インドの瞑想」への魅力は急激に衰えていきました。
この本の誤訳や誤った情報・・・・
ラマナが真我を実現したのは叔父の家の1階ではなく2階であり(イギリス英語ではfirst flour は1階ではなく2階)、ラマナが家出したときの書き置きには「お金は要らない」ではなく、「お金を使って追跡(trace)する必要はない」と書かれていること、母が腸チフスにかかったときのラマナの詩の意味は「どうして火葬が必要であろうか?(母の解脱を予言)」なのに「葬送のために何が必要であろうか」と意味不明の誤訳をしていることなど。
が目につき始め、また、もっとも重要な「TALKS」からの部分訳に当たる第2部が、なんらの系統性もなく、全く恣意的に翻訳箇所が選択され、重要な箇所(理解の難しい)がバッサリと削除されており、最重要文献である「TALKS」の安易な「つまみ食い」に過ぎないことを知るに及んで、ラマナのデヴォーティにとっては「許し難い」書物であるとの感さえ抱くに至ったのです。
(ただし先生個人としては、「この本に導かれてラマナを知り、のめりこんでいく契機となった本である」・・とは言われていた)
そんな事情もあってサイト管理人としては「初心者入門用としてはかなり秀逸な編集」だとは感じつつも、あまり高く評価出来なくなっていた・・・そこへ持ってきて「TALKS」が翻訳出版された今日にあっては、この本の「書籍としての価値」は大幅に下落したのではないか?・・とすら思う。
しかし、この書籍を「不当に評価する」のは間違いではないか?・・・と最近になって考えなおすことになった。確かに「かなり問題の多い書籍」であるし、「TALKS」が翻訳された結果大いに価値を減じたことは事実として致し方ないとしても、
おおえ氏の「情熱」までも批判するのは果たして適切なのだろうか?・・・という疑問である。
まだ全然ラマナの事が知られていない当時にあって、おおえ氏は「このラマナという存在と教えを是非日本にも紹介したい!!」という強い情熱でこの作業にあたられたはずである。その結果としてあれこれ問題を孕み不幸な扱いを受ける羽目になってしまったのだが、それはいうなれば、
「純粋なる熱意のオーバーラン」・・・なのではないだろうか?